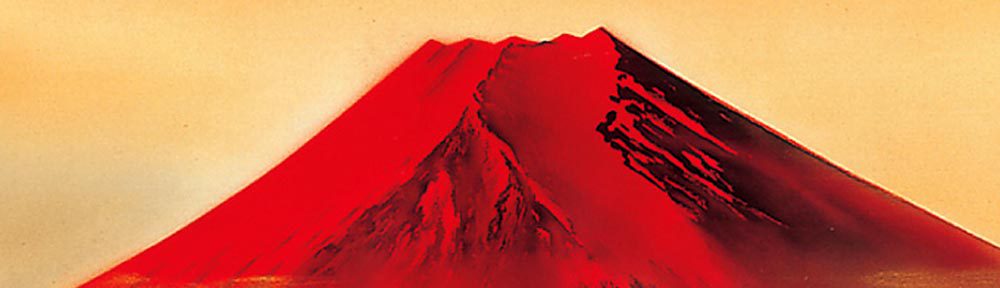☆★☆ 金環日食 ☆★☆
金環日食が近々あることは知っていた。という程度の関心しかなかった。
連日テレビで取り上げられ、大騒ぎになっているので、知らずとも知ることになるわけだが、だからと言って、いついっか、何時に起こることやら、まったくと言っていいほど予備知識もなかった。
金環日食がどういう現象で、どうして起こり、なぜ「金環」なのかも、いろんな写真を見ていたので知っていたから、ことあらためて見たいという願望もなかったのだろう。
5月21日月曜日のあさ7時少し前、犬の散歩に出かけようとしていたら、点けているテレビからまた金環日食のことが出ていて、今日あさ7時から8時にかけて見られるという。金環食は関西地方だと7時半少し前だそうだ。
せっかくだから、濃いめのサングラスをかけて外に出た。
快晴だ。先々週に植えられた稲の苗がみるみる育っている。向こうの山は、新緑に輝く広葉樹林の中に幾何学模様を描くくすんだ杉林が嫌なコントラストをなしている。
さっそくサングラス越しにちらっと太陽を見たんだが、ただ眩しいだけで普段の太陽と全く変わらない。時計を見ると7時15分だから、太陽も相当欠けているはずなんだが、眩しいのなんの。こりゃダメだ。テレビでも、直接見ないよう注意していたので、ほんの瞬間にしか見ないんだが、強烈な光線だ。
やがて時刻は7時29分、金環食になっていて、太陽は最大食分(欠ける大きさの割合)は約0.97、面積でいうと90%近く隠れているそうだが、あたりは少し暗くなったかなという程度で、普段の快晴の日とほとんど変わらない。太陽って、こんなに明るいんだ!感動。
結局、金環日食の「き」も観測できなかったわけで、当然といえば当然。人に話しても笑われるだけだ。
ただ一つ、
砂浜の砂に映った自分の影に縁取りがされていて、はじめ乱視が進んだのかなと思ったことが、これも金環食で起きる現象だとか。
間接的にではあるが、世紀の金環日食に触れられたわけで、いつの間にかみなの仲間入りに相成ったという次第。