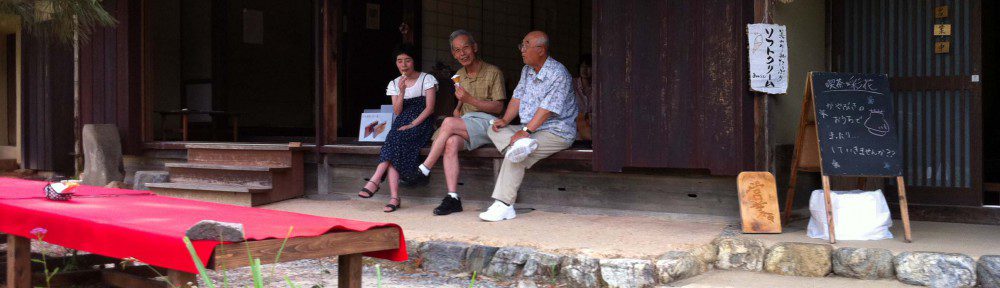♪♪♪ 街のサンドイッチマン ♪♪♪
作詞:宮川哲夫、作曲:吉田 正、唄:鶴田浩二
ロイド眼鏡に 燕尾服(えんびふく)
泣いたら燕が 笑うだろ
涙出た時ゃ 空を見る
サンドイッチマン サンドイッチマン
俺らは街の お道化者(どけもの)
とぼけ笑顔で 今日も行く
嘆きは誰でも 知っている
この世は悲哀の 海だもの
泣いちゃいけない 男だよ
サンドイッチマン サンドイッチマン
俺(おい)らは街の お道化者
今日もプラカード 抱いてゆく
あかるい舗道に 肩を振り
笑ってゆこうよ 影法師
夢をなくすりゃ それまでよ
サンドイッチマン サンドイッチマン
俺らは街の お道化者
胸にそよ風 抱いてゆく
2014年ももう間もなく幕を閉じようとしている。クリスマスも終わり、忘年会もめっきり減ったことだろう。
忘年会でもないが、生徒に誘われカラオケに行くことになった。
年に二三度行くか行かないかで、人に誘われてやっと行くほうで、よく勝手もわからない。持ち歌も大した数はなく古い歌ばかりだ。
そんな中、唯一心から歌える歌がこの『街のサンドイッチマン』である。
以前このブログでも書いた『誰か故郷を思わざる』と同じで、子供のころ、路上に石炭箱を並べて作ったにわかステージで、近所のおばちゃんやおっちゃんが歌う『町内歌謡大会』で初めて聞いた歌だ。
サンドイッチマンに扮した戦闘帽のおっちゃんが、真っ白な顔の両頬にまーるい日の丸を書き、プラカードをふりふり歌っていたその姿と歌いぶりが何とも印象深かった。忘れられない。
ドーナツ盤のレコードを買い、テープレコーダーに入れ、カセットテープに入れ、ウォークマンに入れ、今ではiphoneにまで入れている。
今こうして歌詞を読んでいても胸がジーンとなってくる。歌っている鶴田浩二がまたいい。特攻隊崩れの哀愁漂う歌い振りが心にしみる。
ぼくたちの時代はこんな時代だったんだ。
敗戦から立ち上がり、来年2015年で戦後70年、ずいぶん変わったものだ。この変わりようはぼくたちにしかわからない。
だからぼくの歌う歌は生徒たちにはわからないだろう。聞いてはくれていて、歌い終わると拍手はしてくれるが、お愛想だよおあいそ、優しいお愛想だ。
おなじで、一緒に行った生徒たちの歌はまるで分らない。異邦人の歌かなと思ってしまうほどだ。ちゃかちゃかちゃかとまるで早口言葉のような歌を歌う生徒もいる。なんじゃこれは、という感じだ。
曲探しのタブレットが右に渡り、左に渡り、歌っている人の歌にはまるで関心がない。しかし歌い終わると必ず拍手し、時にはほめ言葉を投げかける。
しかし不思議なことに、ぼくがこの『街のサンドイッチマン』を歌いだすと皆の動きが止まり、じっと耳を傾けてくれる気配を感じる。三番の「あかるい歩道に 肩を振り・・・」と歌いだすと手拍子をし、ぼくが肩を左右に振るのに合わせて皆も肩を左右に振っている。うれしい。鼻の奥がジーンとしてきて、涙が出そうになる。涙を抑えて歌い終わると、みんなが不思議そうにぼくの顔をじっとみている。心が通い合った瞬間だ。
ぼくはこの歌だけはのびのびと歌える。本当に街中をゆくサンドイッチマンになった気分だ。俺らは街のお道化者、胸にそよ風抱いてゆく人生の道化者だという感じだ。
戦闘帽のおっちゃんがのりうつったのか、鶴田浩二がのりうつったのか、自分が歌っている気がしない。大げさで叱られるかもしれないが、生きた時代がのりうつったような気がする。
だからみんなカラオケなんだ。あの四畳半か六畳位の暗い空間は、人が集っていても孤独であり、孤独であるがゆえに歌に浸り、それぞれがしょい込んだ喜怒哀楽をるつぼに溶かし、お互いの絆を確かめ合い、また新たな活力を生み出すブラックボックスなんだ。