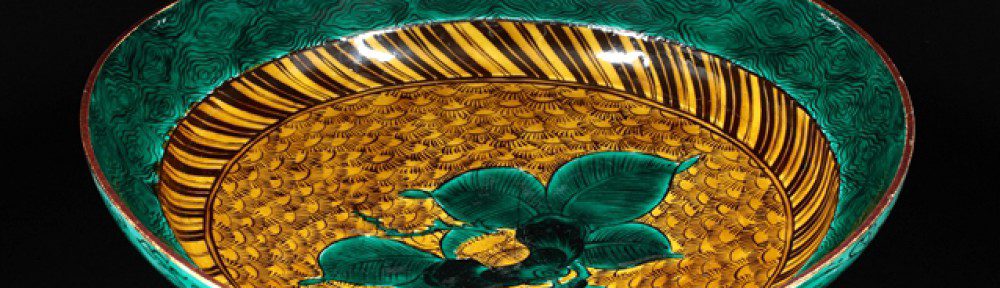昨日、2015年3月30日、『政府、訪日外国人目標を一気に倍増 2020年=4000万人、2030年=6000万人』という見出しが出た。
安倍首相が3月30日、訪日外国人観光客の拡大に向けた具体策をまとめる「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」で、訪日外国人観光客数の目標人数を倍増させ、2020年に4千万人、2030年に6千万人とすることを宣言した。
訪日外国人観光客数が昨年2015年にはすでに1974万人に達しており、2020年の東京オリンピック開催年の目標値の2千万人を大幅に前倒したわけだ。
日本経済は長年、高い技術力を背景に製造業が牽引してきたが、近年は新興国の攻勢にさらされ、株価もITバブル時の高値20833円(2000年4月12日)から下がり続け、途中、2008年9月15日のリーマン・ショック(国際的な金融危機)、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う福島第一原発事故などもあり、やっと第2次安倍内閣が発足した2012年12月以降、「アベノミクス」への期待から2年半で株価も約2倍の20868円(2015年6月24日)にと、ITバブル時から数えて実に15年ぶりに株価も回復した。しかし、その2か月後には8月11日のこれまでの最高値20940円を付けたのちはまたまた下落に転じ、12月1日には一時2万円台は回復したものの長続きはしないで、現在は1万7千円代を行ったり来たりしている状態である。
アベノミクスが打ち出した経済成長戦略の第一ステージ、旧「3本の矢」は「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「投資を喚起する成長戦略」の3つであるが、このうち日銀の協力を得た金融緩和は円安・株高でアベノミクスの基盤を築き、一定の成果を上げたものの、財政政策は一時的な刺激策で評判はいまひとつ。市場が期待していたのが「道半ば」と言われ続け、ここ1年は頭打ち状態。15年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを1年半延期し、17年4月とすることが確定。「景気条項」を削除し、景気情勢次第でさらに先送りできなくなるとしたものの、ここにきて景況判断と夏の参院選対策から再延期もうわさされる始末。新聞各紙もまるで再延期が決定されたかの書きっぷりだ。
そこで打ち出されたのが、アベノミクス第2ステージ、新たな「3本の矢」が、(1)希望を生み出す強い経済(GDP600兆円)、(2)夢を紡ぐ子育て支援(出生率 1.8人)、(3)安心につながる社会保障(介護離職ゼロ)なのである。
昨日の宣言はまさしくアベノミクス新三本の矢の内の(1)、首相が掲げる名目国内総生産(GDP)600兆円の達成に向け、観光立国をその起爆剤にしたい考えを打ち出したわけだ。
日本を代表した企業が、SHARPは台湾企業に買収され、東芝はでたらめ会計も手伝ってボロボロ、SONYはアップアップなど。自動車産業だけは業績を伸ばしているものの、これとていつまで続くやら。
ここで目を付けたのがクールジャパン(格好いいニッポン)で表せられる日本の映画・音楽・漫画・アニメ・ドラマ・ゲーム・カラオケなどの大衆文化の世界的進出。今や日本文化は世界を席巻し、その影響もあってか日本を訪れる外国人は上に示したように鰻上り。中国人観光客の「爆買い」の話題は尽きず、世界から、そして今では東南アジアのさまざまな国から観光客が押し寄せる。これを放っておくのはまさしく「もったいない」。
日本は「気候」「自然」「文化」「食」という観光先進国の4条件がそろっている。政府としては観光産業のてこ入れを図ることで円高株安の打撃を受けにくい筋肉質の経済への転換を図りたいと考えたわけだ。
首相は会議で「観光は成長戦略の大きな柱の一つであり、地方創生の切り札だ。世界が訪れたくなる日本を目指し、観光先進国という新たな高みを実現していく」と述べた。
首相が掲げる新三本の矢「名目GDP600兆円」「希望出生率1.8」「介護離職ゼロ」のうち、子育て支援や高齢化対策などの社会保障制度改革は政策効果が出るまでに一定の時間がかかる。一方、観光はインフラ整備からサービス業まで裾野が広く、景気回復へ即効性が期待できると判断したわけに違いない。
政府、安倍首相の意図はともかく、世界から日本にやってくる人たちが増えることに異存はない。
これまでの日本への関心の大部分は、1968年、戦後23年にしてGDP世界第2位になるというその経済力が中心だったわけだが、今やクールジャパン、つまり日本の伝統に深く根差した文化によって、世界の人々を招来しようとするわけだから、共感と信頼を得ればこれほど安定した成長力はないし、世界の平和と安定に寄与するものはない。
ところで、これだけ日本に注目が集まり、訪日外国人数が増えているとはいえ、2014年度における「世界各国・地域への外国人訪問者数」の統計を眺めてみると、1位のフランスが8400万人、2位アメリカが7500万人、3位がスイスの6500万人で、日本は1350万人で世界22位なのである。そしてアジアでも7位というから驚きだ。もちろん2015年には訪日外国人数が激増して2000万人にちょっと足らずというところに来たわけだから、これで、韓国1420万人、マカオ1450万人を抜いてアジアでは4位、タイの2500万人に次ぐことになる。
2030年の目標値6000万人は、アジアNo1の中国5500万人を多分に意識した数値目標であるところが面白い。
いずれにしろ、外国人訪問者数だけでは、世界で注目される国の度合いは計れない。クールジャパンは今や世界の標準語になりつつある。
世界の最東端、極東に位置する日本はあらゆる意味で世界から最も遠い国であったわけだが、今や交通手段はひと昔前に比べても世界を縮め、もう日本は遠い国ではなくなった。
日本の経済力だけではなく、日本の風土と文化に関心を持って訪れる外国人は本物だ。大切におもてなししたいし、期待にたがわない文化をさらに発展させたいものだ。