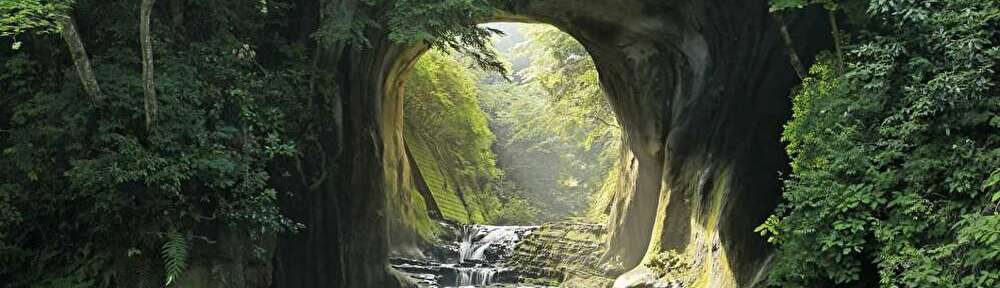I was induced by the merry of spring and followed the Koya Old Highway. I enjoyed the arts while drinking Yuzu tea at a gallery on the way. I still have a long way to Koyasan.
昨日は河内長野市にある高野街道沿いの画廊『ほたる』にお邪魔しました。友人のグループが個展を開いていて最終日だということで駆け付けたというわけです。
80を越えた老先生を中心に中高年の生徒さんが集めっておられて、皆さん絵もなかなかお上手。最近こうして中高年から始められる方が多いとか。もともと絵心もあったからでしょうが、短期間でこんなに素敵な絵が描けるのかとびっくりした次第です。
絵もさることながら、街並みが気になり、周りを散策すると、街道沿いには重要文化財に指定されている酒造会社跡があったり、どの家の間にも『高野街道』と書かれた門前灯篭が立てられていたり、なかなか風情があります。
『高野街道』はその名の通り高野山への参詣道で、大阪や京都から高野山にお参りするには、先ずこの河内長野に来て、そこから県境の紀見峠を越え和歌山県の橋本市に出て高野山にお参りします。
今はこのあたり一帯は大阪のベッドタウン化が進み、高野街道もズタズタ。最近になって昔の景観を保存しようと、この画廊周辺も再整備されたそうです。
熊野街道と高野街道は昔は多くの人が行き交う幹線道路で、宿場があり、温泉があり、遊郭あり、相当賑わったそうですが、今ではこうした町興しの一環になっているだけです。
長野神社にお参りして家路につきました。