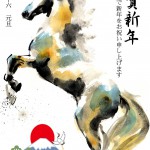ゴールデンウイーク中の4日間、久々に連休が取れたので山陰地方を巡ることにした。
噂の竹田城、天空の城として今人気のスポットだが、ちょっとミーハー気のあるぼくは先ずここを訪ねたいと思っていたことと、長年一度は行ってみたいと思っていた萩が結びついての山陰旅行と相成ったわけだ。
途中にも、兵庫の生野銀山、松江から出雲大社、世界遺産石見銀山、石見の柿本人麻呂事績、まだ訪れたことのない場所がいっぱいあって、できたら訪れてみたいとの胸ふくらませての旅立ちだ。
旅程、車でおよそ600km、往復で1200kmだから、4っ日間3泊で行くには少し無理があるかもしれない。
いつものことながら、高速道は利用したくない。ただひたすらに目的地の向かって走るだけで、途中の景色を見るゆとりもなければ、寄り道してみる面白さもないから嫌だ。車での旅は一般道に限る。
とりあえず、生野銀山と竹田城はそれほど離れていないので一日目はここを目標にと出発した。
このあたりには友人の家もあったし、西国33か所めぐりや城崎温泉なんかにも何度か行ったこともあったので知らない場所ではなかったが、竹田城のことは今回初めて知った。
2、3年前だったか、NHKの大河ドラマ『江』で有名になった同じ山城「小谷城」にも行ったことがあるが、ただしんどいだけであまり印象にも残らなかった記憶がある。
竹田城は違った。噂に違わず、天守閣や建物の遺構こそなかったが、累々と積み重ねられた石垣はしっかり残り、「東洋のマチュピチュ」とはちょっと言い過ぎだが、確かに天空の城の威風は感じられた。
国道9号線を辿り、いよいよ日本海が見え始める頃になって驚いたのは、五月晴れという天候の性もあるが、実に明るい風景が目に飛び込んでくることだった。
真っ青な海と打ち寄せる真っ白な荒波はまさしく日本海だ。
それに道がいい。9号線もそうだが、建設中の山陰自動車道が一般道と同じように利用でき、いわゆる高速自動車道の不便さがないし、実に快適だ。全線開通していなくてプツンプツンと好きなところで出れるのがいい。有料区間も260円とか450円とか数か所で払うだけで、ほとんどがまだ無料区間になっている。
5月5日こどもの日に合わせていたるところで催し物が開催され、出雲では古式豊かな出雲舞が披露されていた。
人があふれ、踊り、食べ、みんな実に陽気だ。「山陰」とは裏腹な景色と光景が展開されているのには驚かされた。
今から50年以上も昔、国鉄の周遊券で山陰線、山陽線を辿ったことがあるが、その山陰線が並走しているところもある。しかし列車にはとうとう出会うことはなかった。
時代が変わったんだ。
浜田辺りで列車の中から見えた日本海の夕日はいまだに残像として残っているが、今はセンチメンタルのかけらもない。あたりの明るい光景があまりにも強烈だからだ。
寄り道しすぎて時間がなくなった。最終目標の萩を目指すことにした。
萩は期待通り落ち着いた街で、町中いたるところに歴史が刻まれていた。
萩城の一角は石垣の中に民家が散在し、今流行りの時代街にもなっていてたくさんの焼き物の店がある。どれも凝った店造りだ。
萩城跡の指月公園に入ると琴の音が流れてきた。藤の花がたわわに垂れ下がったその下で何面もの琴が演奏されていたのだ。
その奥に「花江茶亭」があった。13代藩主・毛利敬親が安政5年(1858)旧三の丸にあった藩主別邸花江御殿内に増築した茶室で、明治期に指月公園内に移築され、幕末期、敬親は家臣たちと茶事に託して時勢を論じ、国事を画策したといわれている、まさに文明開化期の茶亭だ。
今日はその茶亭で表千家の大茶会が催されていて、迷わずお点前頂くことになり、しばし明治に思いを馳せる機会を得た。
もう一つのお目当ては「松下村塾」である。
その佇まいの小ささにまずびっくり。8畳と10畳の二部屋しかない。この小さな塾から、高杉晋作をはじめ、伊藤博文、山縣有朋など明治維新で新政府に関わる人間をあれほど多く輩出したとはとても思えないほどだ。
藩校明倫館とは違い、武士、町人の身分を分け隔てなく受け入れた自由と革新の気風がこの小さな掘立小屋に凝縮されていたことを想い、思わず目頭が熱くなった。
もうこれで十分だ。
津和野に向かう田園風景は実に心癒され、今回思い立った旅路が歴史と明るい未来をつなぐ自分なりの納得のいく旅路だったことに満足した。