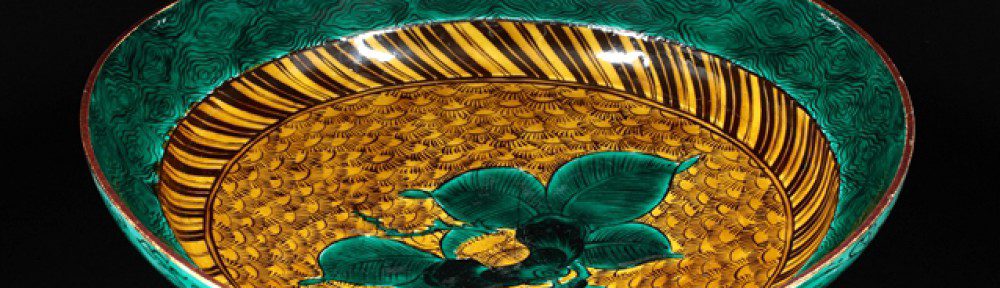♪♪♪ 笛吹童子の歌 ♪♪♪
1989年のイタリア映画で「ニュー・シネマ・パラダイス」という映画がある。ご存知の方も多いだろう。 映画好きの少年トトと「シネマ・パラダイス」の映写技師アルフレードの友情と、数奇な運命をたどるトトを描いた感動の名作だ。 ※あらすじはこちら⇒http://www7a.biglobe.ne.jp/~eigatodokusyo/syuminoheya/eiga/eiga-1/eiga-11/paradaisu.htm 「ニュー・シネマ・パラダイス」がトトのノスタルジーであったように誰にも語っておきたいノスタルジーがあるに違いない。 「ヒャラーリヒャラリコ ヒャリーコヒャラレード・・・」 この音楽が聞こえてきたらもう居ても立っても居られない。5球スーパーラジオの前に座って、雨が降ろうが槍が降ろうがわれ関せずの構え。 憎っくき赤柿玄蕃を菊丸(笛吹童子)よ何とかやっつけてくれと、拳を固めて血湧き肉躍ったものだ。 毎日夕方5時45分から始まるので、冬場はいいが、日の明るい季節のころは大変だ。 当時は学校が終わってもすぐには家に帰らない。放課後は大概校庭で、小使いさん(校務員)に追い払われるまで野球なんかをしていたから、5時半位になると気が気でない。野球好きな奴が帰さない。これとの戦いが大変だった記憶がある。それでも毎日聞いていたから、多分うまい具合にやっていたんだろう。 「音楽 福田蘭童」もはっきり覚えている。後で知ったんだが、この「福田蘭童」、明治の洋画家、「海の幸」で有名な青木繁の息子で、蘭童の息子がクレジーキャッツのピアニスト石橋エータローというそうだから、ここまでくればやっと一世代後の諸君と接点があろうかと。 そして夜が明ければ、今度は「少年ケニア」だ。 アフリカのケニアを舞台に、孤児になった日本人少年ワタルが仲間のマサイ族の酋長やジャングルの動物たちと冒険をする物語で、「産業経済新聞」(のちの「産経新聞」)に連載されていた。 朝起きると、いの一番に朝刊を取りに行き、誰にも開けられていない新聞を開くときのインクの匂いが今もツンと鼻に残っている気がする。 山川惣治原作の絵物語でこの挿絵が実に良い。当時「産業経済新聞」は「ケニア新聞」とも呼ばれたそうだから、その人気たるや推して知るべしである。 そして月に1回。今度は雑誌「少年」である。 江戸川乱歩の「怪人二十面相」。探偵明智小五郎が助手の小林少年とともに怪人二十面相に立ち向かう物語は少し怖かったけれども布団をかぶりながら読んだものだ。 手塚治虫の「鉄腕アトム」は言わずと知れた日本アニメの元祖。実に夢があり、この「鉄腕アトム」に刺激されて様々な分野で羽ばたいた人も多いはず。未来を予見した作品だった。 発行日には必ず父が買ってきてくれ、その日はもう朝からわくわくだ。待ちきれなくて駅まで父をよく迎えに行ったことがる。 それに付録がまたこれが圧巻。今でも鮮明に覚えているが、紙製の組立幻灯機や映写機とかがあって、それを完成させて家族全員に見せたところ、全員が感動してくれていっそうの励みになった。 これらすべてが小学校低学年頃の思い出だ。 そうそう、もう少し学年が進んだころと思うが、ほのぼのと思いを寄せていたハットリさんが、NHKのラジオドラマ「君の名は」が好きだと聞いたんで、夜何時だったか同じ思いを寄せたくて聞いたものだ。ハットリさん、今はどうしているんだろうなあ。