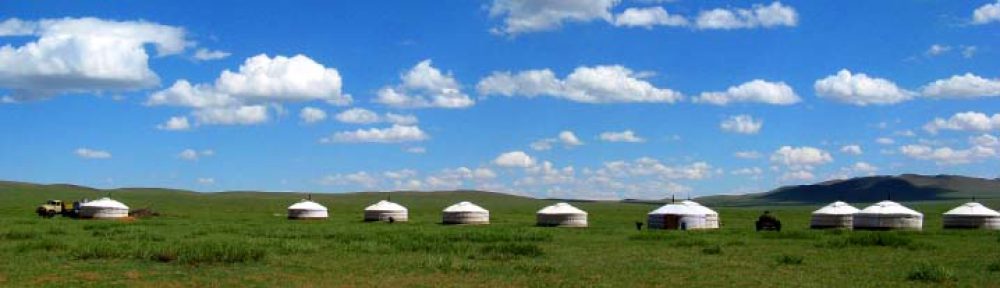On August 6, 1945, 8:15 am, the first atomic bomb was dropped in Hiroshima for the first time in history. By the end of the year, there were approximately 140,000 deaths. From this estimate, it is estimated that approximately 100,000 people died in an instant. We must never forget this day when the most stupid act took place in the human history.
1945年8月6日午前8時15分、人類史上初めての原子爆弾が広島に投下され、同年末までの犠牲者が14万人と推定されていますから、その半数としても少なくとも7万人は瞬時に亡くなったと推定されます。
日本の敗戦が確実視され、その敗戦処理を巡って国際社会が動く中、原爆投下の意味がいまだに問われています。
1922年に誕生したソビエト社会主義連邦共和国を中心とした共産主義国家の台頭と、アメリカを中心とした資本主義国家の戦後世界の力関係が反映したという意見もあれば、当時のアメリカ大統領トルーマンの個人的な資質に原因を求めるものなど、国家から個人まで様々な要因が絡んでの原爆投下ではありましたが、たった一個の兵器でこれほどまでの殺戮が行われた事実は厳然として残ります。
戦後74年、いまだに戦争は絶えませんが、原爆のような大量殺戮兵器が使われていないのはこの広島の惨禍が人類の脳裏に焼き付いているからに他ありません。しかし、この記憶もだんだん色褪せ、またいつ何時この原爆が使われないとも限りません。
広島の時は、世界でたった2発の原爆があっただけですが、いまは世界に何万発もの原爆が保有されています。
一人一人がヒロシマの記憶を忘れず、原爆の恐ろしさを世界に伝えていくことは大切です。