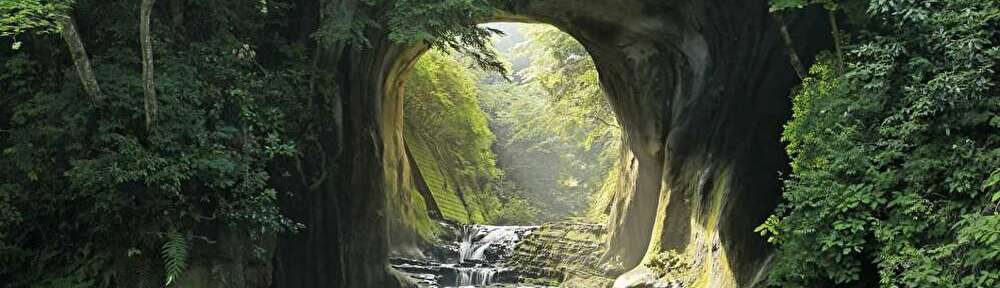NHK ‘s morning drama has finally come into its climax. Impressed by it, today’s breakfast is “Reprint edition instant ramen”. I ate delicious, remembering a lot of things at that times.
NHKの朝ドラ「まんぷく」は毎回見ています。いよいよドラマも佳境に入って、即席ラーメンは完成し、「まんぷくラーメン」と命名されました。
昨日はそれに惹かれてか、さっそく近くのスーパーに出かけたら、入り口に「1958年復刻版パッケージ」と刻印された即席ラーメンが並んでいます。商魂たくましいというか、お客の要望あってのことか、ともかく買い求めました。
今朝はこれで朝食です。栄養と健康のことを考えて、お肉や野菜をたっぷり入れ、お鍋で煮たわけですから、インスタントラーメンの食べ方とはちょっと違ったかもしれませんが、美味しかったです。
麺が実にいい。昔はこんなだったか、思い出せもしませんが、復刻版といっても当時のそのままではなく、麺も今の技術でできた麺なんでしょう。
食べながら、昔のことを思い出しました。
京阪沿線の千林駅を降りると千林商店街という、当時はかなり繁盛した商店街があり、その入口に「主婦の店ダイエー」というスーパー・マーケットのはしりの店があって、中内のおっちゃんが枚掛けをして「いらっしゃい、いらっしゃい」とお客を呼び込んでいました。後の「スーパー・ダイエー」ですね。中内のおっちゃんこそ、その創業者で、日本で初めてのスーパー・ストア、「ダイエー」を築き上げた人です。
そこにこのインスタントラーメンがうず高く積み上げられていました。
それと当時これも珍しいコカ・コーラとを買って、時々、これもまだ創業間のない「餃子の王将」で餃子を食べて、家に帰ったものです。
あれやこれや、もう昔昔のことが思い出される朝食になりました。