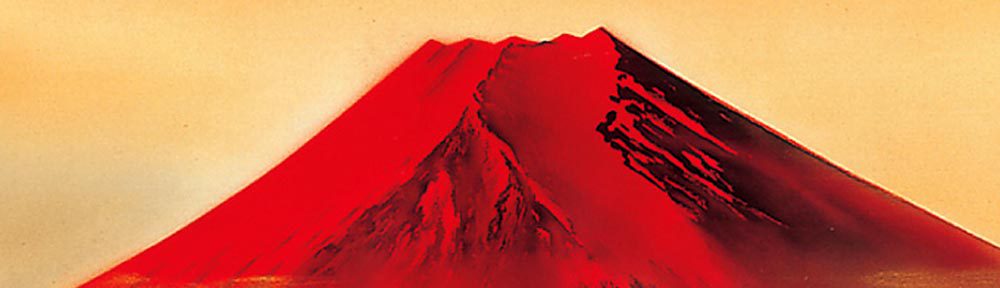久しぶりで骨のある読み物を手にし読破することができた。数学好きの高校生諸君にはぜひともこの夏の読み物として読んでいただきたい。いや数学好き、また高校生諸君だけではない。物事にまともに取り組もうとする人であればだれもがきっと夢中になって読める本だと思う。平成18年6月1日に初版が発行され、平成20年6月10日に15刷が発行されているのだから、もうずいぶん多くの人が読んでいて、ぼくが紹介するのもおこがましい限りだが、それでも呼びかけたいと思える本だ。
前置きは長くなったが、この記事のタイトルにも書いた「フェルマーの最終定理」という表題で、著者はイギリス生まれのインド人サイモン・シン、訳者は青木薫という女性物理学者による「感動の数学ノンフィクション!」、500ページの新潮文庫本である。
面白いのは、著者も訳者も最初は数学を志したが、最後は物理学に進んだ経歴の持ち主ということだ。著者サイモン・シンはその後英テレビ局BBCに転職し、今は作家生活というからなお面白い。数学に対する憧れと羨望の気持ちは持ちながら、自分の才能と適正を判断しての方向転換だったのだろうが、数学の持つ美しさは忘れられず、門外から眺めた数学だからこそ、もっと門外漢である僕などにも分かりやすく、わくわくさせながら読ませたのだと思う。著者の力量と訳者の手腕がマッチした実に読みやすい本だ
「フェルマーの最終定理」はそれこそGoogleの検索にかけてもらえばすぐにでも概要はつかんでもらえるだろうから詳しい説明は省かせてもらうが、1600年代初頭のアマチュア数学者フェルマーが、本職の法律書の余白に書き残したきわめてシンプルな定理である。誰もが中学校の数学で学んだ「三平方の定理」またの名を「ピタゴラスの定理」と聞けば「ああ」とおぼろげにでも思い出せるあの定理を発展させたものだと思えばいい。
このアマチュア数学者が提出し「真に驚くべき証明方法」を発見したが余白がないので書き残さなかったというこの「大定理」に、過去360年間世界の名だたる天才数学者達が挑戦してきたがついえず、しかしその過程で数学のすそ野が大きく広がり、数学発展に大きく寄与した点でもまさしく「大定理」なんだが、「底なし沼」に吸い込まれていった人たちも数知れず、「数論だけには手を出すな!」と言われるほどの魔境でもあったわけだ。
そして20世紀も残り少なくなった1995年,ついにイギリス人数学者アンドリュー・ワイルズがこの「フェルマーの大定理」の証明に悪戦苦闘の末成功したわけだが、この本にはワイルズの戦いぶりとそれにまつわる様々なエピソードが盛り込まれていて、中でも日本人数学者、谷山、志村両氏の提出した「谷山・志村予想」というこれまた数学での難問題が、ワイルズの成功に大きく示唆を与え、貢献したことを正当に評価している点などもわれわれ日本人の心を揺さぶる。
関心のある人にはぜひとも一読をお勧めしたい一冊だ。